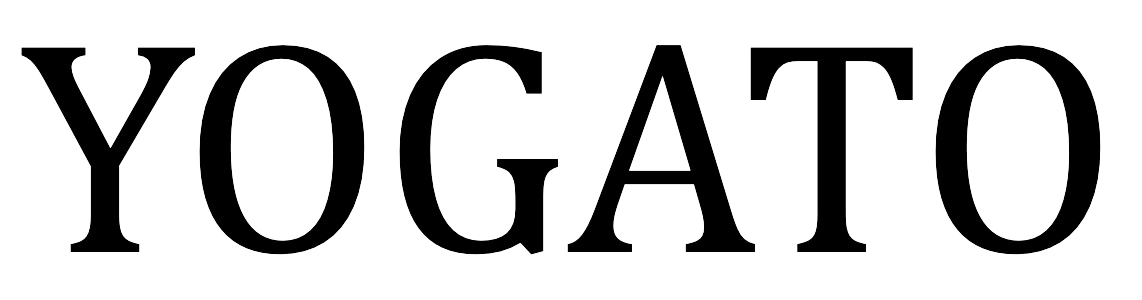ヨガと暦と。[大暑]
二十四節気(にじゅうしせっき)/大暑(たいしょ)
7月22日頃〜8月6日頃
一年でもっとも暑さが厳しくなる頃。
朝も夜も気温が下がらず、
からだの熱も、気持ちの重さも、
じんわりと内にこもりやすくなっていきます。
けれど、この時期の自然は、
いのちのエネルギーにあふれています。
太陽を浴びて育つ稲や夏野菜、
空をわたるセミの声、夕暮れの風。
すべてが「今」という季節の鼓動を伝えてくれています。
だからこそ、わたしたちもまた、
“夏の気”とうまく調和しながら、
熱をやさしく発散し、こもらせないように。
そのための小さな養生が、
この夏を軽やかに乗りこえる手助けになります。
大暑におすすめのヨガのポーズ
こどものポーズ(バラーサナ)
陽のエネルギーが満ちるこの時期には、
“ふっと頭を下げる”やすらぎのポーズが、内側に静けさをもたらしてくれます。
こどものポーズでは、背中や肩の力を手放し、
おでこを床に近づけることで、自然と深い呼吸が戻ってきます。
熱をやさしく地におろすように、
この姿勢のまま、ゆっくりと呼吸してみましょう。
呼吸とともに、からだも心も、少しずつほどけていくのを感じられるかもしれません。
夏の盛り、まぶしい陽ざしに包まれているようでも、
自然界ではすでに、夏至を過ぎ、“陰”の気がほんの少しずつ芽吹きはじめています。
そんなときに「頭を下げる」というシンプルな動きは、
外に向かっていた意識を、自分の内側に静かに戻す手助けになります。
あわただしさを手放して、自分の呼吸のリズムに気づくための、
やさしい入り口として取り入れてみてください。
(※補足✨真逆の動きである、
仰向けで胸を開く「魚のポーズ」もおすすめです。
前回 https://yogato.jp/ヨガと暦と%E3%80%82小暑-2/
ご紹介した「コブラのポーズ」と同様に、
胸をひらくことで、熱がこもりやすい上半身からやさしく熱を逃がし、
呼吸を広げる助けになります。
座るのがつらいときや、腰を伸ばすと痛いと感じるなど、
横になってリラックスしたいときは、
こちらのポーズもぜひ試してみてください。
背中の後ろに腕を入れるだけでも十分胸が開かれます。)
大暑のころの養生ポイント
・熱をこもらせず、やわらかく逃がす
エアコンで冷やしすぎないように気をつけながら、
朝や夕方の涼しい風を取り入れたり、
ぬるめのシャワーや濡れタオルで首筋を冷やしてクールダウンを。
・食事は“冷やしすぎ”を避けてバランスよく
冷たい麺類やさっぱりしたものに偏ると、内臓が冷えてだるさの原因に。
梅干し・しそ・みょうがなど“香味”を取り入れて、
消化を助けながら元気を保ちましょう。
・早朝や夜に、五感をひらく
暑さで感覚が鈍りやすいこの時期こそ、
朝の涼しい空気、夕暮れの空や音に、心を澄ませてみて。
自然の気配にふれることは、自律神経の調整にもつながります。
暑さの中にある「静けさ」を感じる
大暑は、一年でいちばん“陽”のエネルギーが満ちるとき。
でも同時に、ほんのすこしずつ“陰”が生まれはじめる節目でもあります。
がんばり続けるのではなく、
すこしだけ立ち止まって,
“いま”の自分にやさしく目を向けてみましょう。
暑さの中にも、呼吸の静けさや、内なる涼しさは確かにあります。
それに気づくこともまた、夏を元気に過ごす智慧のひとつです。
次回のメールマガジンでは、詳しい食養生コラムをお届けします!
養生、セルフケア整体のこと、
もう少しマニアックな話などもお届けしていますので、
メールマガジンもどうぞご登録ください。
👉 [メールマガジン登録はこちら]
一番暑い時期だからこそ、
無理をせず、
“やわらかく、ととのえる”という選択を。
自然のリズムに寄り添いながら、
からだと心をゆるやかに整えていくヨガと養生を、
共に大切にしていけたらうれしいです。
自分の心地よい養生で、この夏ご自愛くださいね。
YOGATO うおざきよしこ