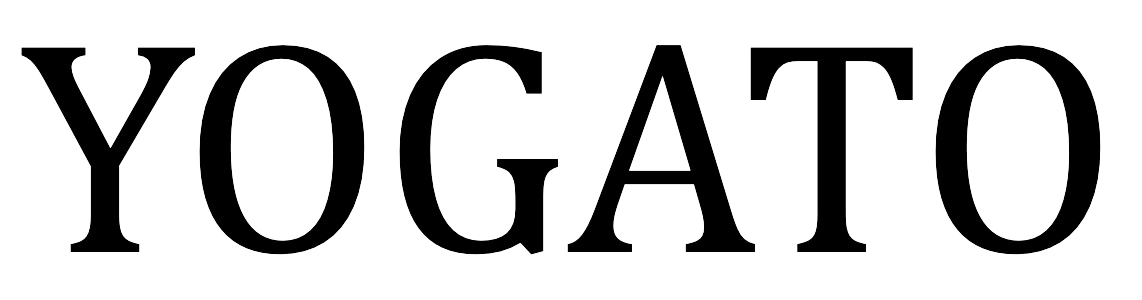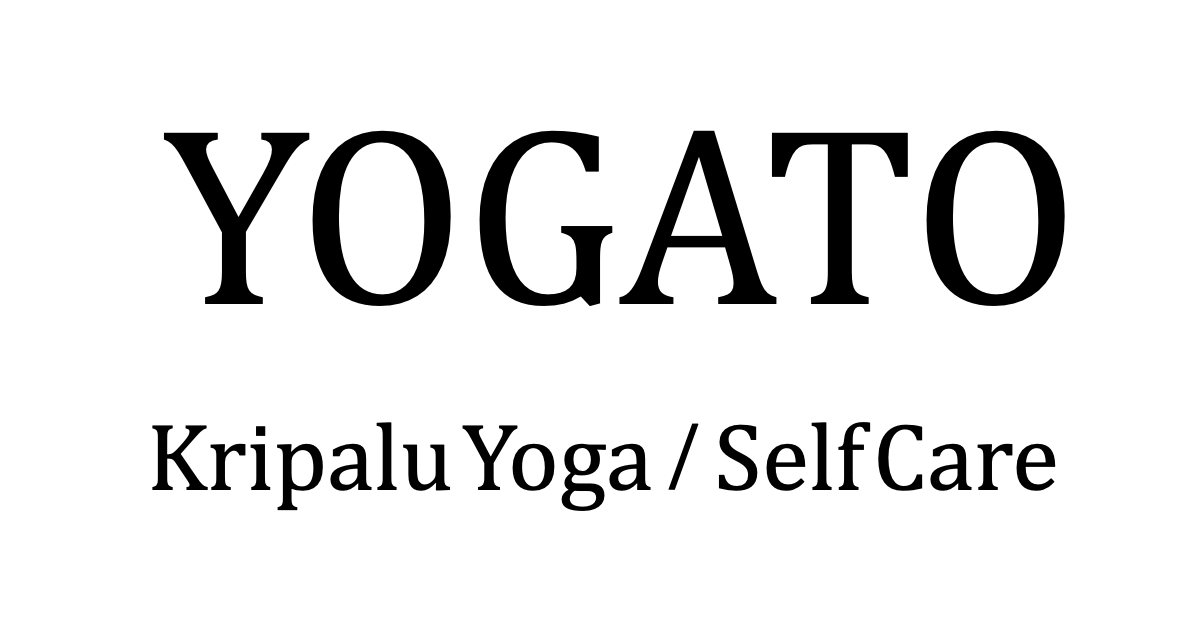<「疲れが抜けない」その奥にあるもの – 副腎と食養生の視点から>
近年、整体や自然療法の分野で「慢性疲労=副腎疲労では?」
という言葉を耳にすることが増えてきました。
これは、医学的な診断名ではなく、
日常的な疲れや不調の原因を、より細やかに理解しようとする試みの一環かもしれません。
副腎とは、腎臓の上にちょこんと乗っている小さな内分泌器官で、
私たちのからだにとって非常に重要な役割を果たしています。
ここ「副腎」では、コルチゾールやアドレナリンといった「ストレスホルモン」が作られ、
私たちが日々動くために必要なエネルギーを供給します。
これらのホルモンは、
プレッシャーの中で頑張ったり、朝起きたりするために欠かせないものです。
しかし、現代社会では休む時間が少なかったり、
常に心が忙しく動いていたりすることが多いため、副腎は「非常事態だ」と判断し、
ストレスホルモンを出し続けることになります。その状態が長引くと、
副腎は「もうこれ以上ホルモンを出せません…」と機能が弱まり、
私たちに「不調」の形でサインを送るようになります。
朝起きられない、イライラしやすい、食後すぐに疲れる、
甘いものがなかなかやめられない、そんなときがそれにあたります。
YOGATOでは、ヨガにツイストのポーズやお腹をほぐすセルフケア整体、
そして「腎」の手あての時間などを通じて、この副腎の声にも静かに耳を傾けています。
副腎が疲れているとき、これらのケアが優しく心とからだに届き、
「もう頑張らなくていいよ」と伝えてくれるのです。
そして、副腎の疲れを癒すためには、食養生が非常に大切です。
適切な食材を摂ることで、副腎をサポートし、日々の疲れを和らげることができます。
以下の食材や過ごし方は、副腎に優しく働きかけてくれるものです。
・副腎をいたわる、やさしい食養生のヒント
1.「黒いもの」で腎を養うことが副腎にも共通
黒豆、黒ごま、ひじき、きくらげ、黒米などは「腎を補う食材」として知られ、
古くから大切にされています。これらは副腎にも良い影響を与える食材です。
2.ミネラルと天然の塩分を少しずつ
副腎が疲れていると、ナトリウム(塩分)をうまく保持できず、
しばしば塩気を欲するようになります。にがりを含む天然塩や、
味噌、梅干し、昆布などを少しずつ摂り入れて、副腎を優しくサポートしましょう。
3.甘いもので補うなら、「滋養の甘さ」を
副腎が疲れているとき、甘いものを欲しがることがあります。
そんなときには、白砂糖よりもきび砂糖や甜菜糖を選び、
かぼちゃやさつまいも、干し芋、甘酒、小豆などの自然の甘みを摂るようにしましょう。
特に「もちもち」「ねっとり」した食感のものが腎に良いとされています。
自然な甘さで副腎を癒すことが、甘いものを減らす近道になるのだと思います。
4.冷たいもの・刺激の強いものは控えめに
副腎は冷えに弱い部分です。氷水やアイス、
過剰なカフェイン、香辛料などは体に過剰な刺激を与えすぎることがあり、
副腎に負担をかけることがあります。
なるべく温かい食事を心がけ、内からからだを温めることが大切です。
・ ・ ・
疲れが取れない日、なぜか眠ってもすっきりしないと感じることがあります。
それは、決して「怠けているから」ではなく、
副腎が「もう少し休ませて」とそっとサインを送っているのかもしれません。
そんなときには、ヨガマットの上でふっとみぞおちの裏側の背中に手を添え、
優しく背骨をツイストしてみましょう。
あたたかい黒豆ごはんをゆっくり噛むことや、
ぬるめのお湯でほっと息をつくことも、副腎をいたわるための大切な方法です。
自分自身を大切にすること、からだの声に耳を傾けることが、
最終的には深い癒しと元気を取り戻すための鍵です。
日常の疲れに立ち向かいやすくなり、
穏やかな日々を送ることができるのです。
今日の配信動画『おやすみYOGATO』では、この副腎疲労にアプローチします。
ゆったりと静かに呼吸とともにヨガと手当てもしてみてくださいね。
今日も最後まで読んでくださり、ありがとうございます。