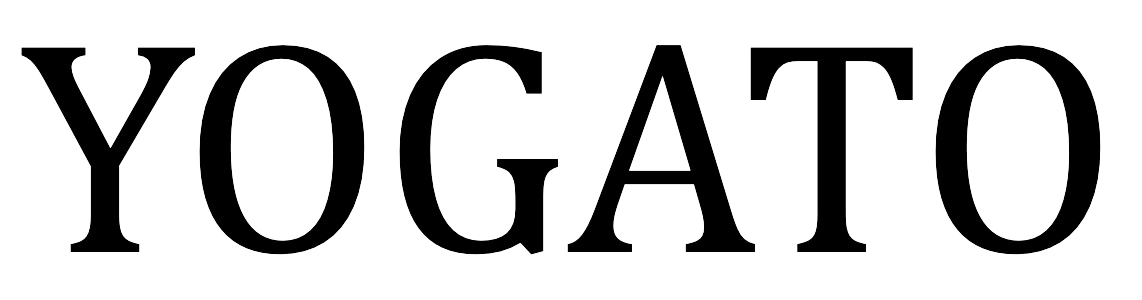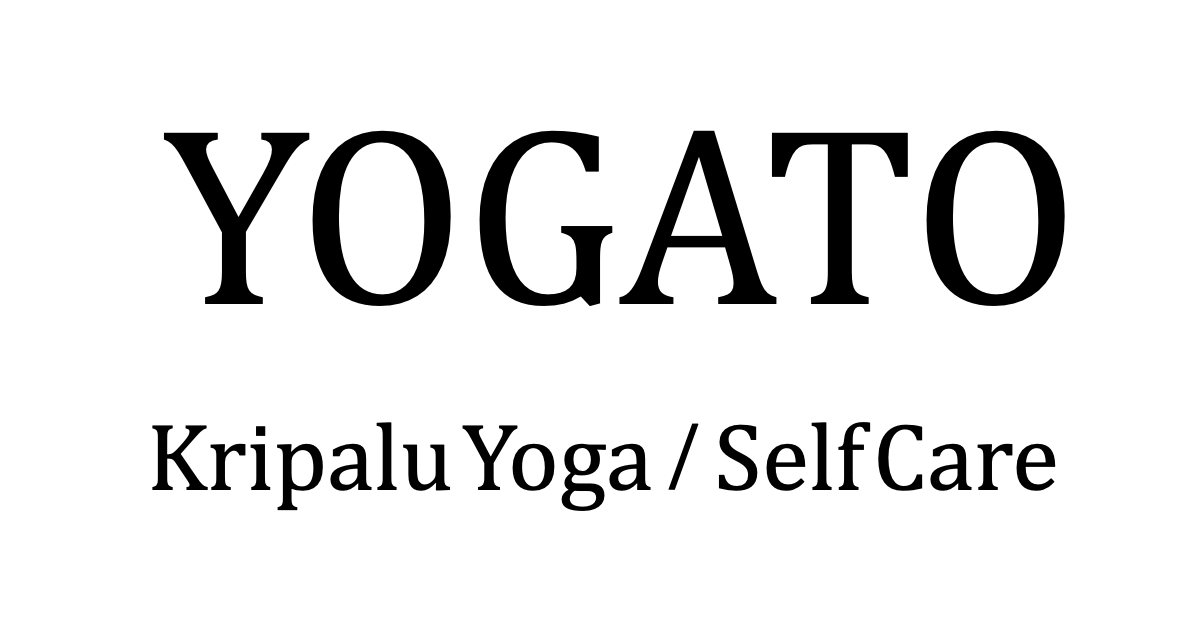<“脾”は脾臓じゃないの?!——臓という言葉の奥にあるもの>
最近のクラスや前回のメルマガでもよく登場している「脾」や「肝」という言葉。
実はこの「脾」や「肝」、
わたしたちが現代医学で思い浮かべる「脾臓」や「肝臓」とは、
まったく同じではないのです。
たとえば…
「脾経って、脾臓のこと?」
「肝が疲れてるって、肝臓の数値が悪いってこと?」
そんなふうに思われる方も多いのではないかと思います。
でも、東洋医学の世界では「脾」や「肝」は、臓器というよりも、
からだとこころを支える“はたらきのまとまり”として考えられています。
たとえば「脾」は、現代医学で言えば、消化や吸収のはたらきに近い部分があります。
けれど、それだけでなく、水分代謝や血液の流れ、思考の安定、
そして“からだの真ん中”を支えるような役割も担っています。
「肝」は、もちろん肝臓そのものも影響を受けるラインではありますが、
それ以上に、気のめぐりや感情の調整、筋肉や腱、
目の状態などにも深く関係しているとされています。
これはつまり、「臓器を“形”として見る」のではなく、
臓を“はたらき”として見るという、東洋医学ならではの世界観です。
たとえば、こんなふうに・・・
・肝は「めぐり」
・心は「熱と意識」
・脾は「吸収と統合」
・肺は「呼吸と浄化」
・腎は「貯蔵と根本の力」
このように、からだ全体の流れの中で「何を担っているか」という視点で臓を見ていくと、
「不調=どこかが壊れている」ではなく、
「少し流れが偏っている・整っていない」ことに気づきやすくなります。
そしてその視点が、日々のセルフケアや呼吸、動き、
養生の在り方を、やさしく整えてくれるように思うのです。
ちなみにこの「脾」や「肝」のはたらきは、経絡(けいらく)の流れにもあらわれています。
・脾経は、足の親指から脚の内側を通って、お腹の真ん中へ
・肝経は、足の親指から脚の内側を通り、肋骨・胸下へ
どちらも、内側から自分自身を支えるようなラインです。
やさしくなでたり、ツボを押したり、ヨガの動きの中で意識するだけでも、
からだの感覚や呼吸が、ふっと変わる瞬間があります。
「臓器を見る」のではなく、
「臓のはたらきを感じる」。
その視点は、見えないものを感じとる、
とても繊細で豊かな感覚です。
そして何より、からだってやっぱり面白い!
よーく精密にできているんですね。
そう思えることが、養生やセルフケアを無理なく、
自然なものにしてくれるのだと思います。
YOGATOのクラスでも引き続き、
そんな“見えない流れ”に触れるような時間をお届けしていきますね。
今日も最後まで読んでくださり、ありがとうございます。