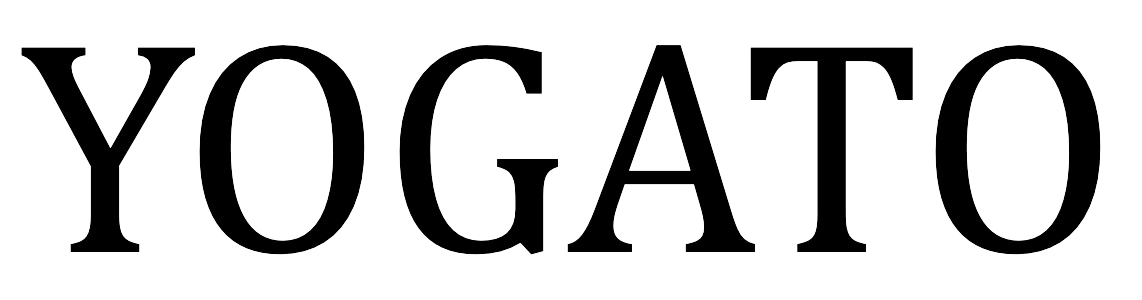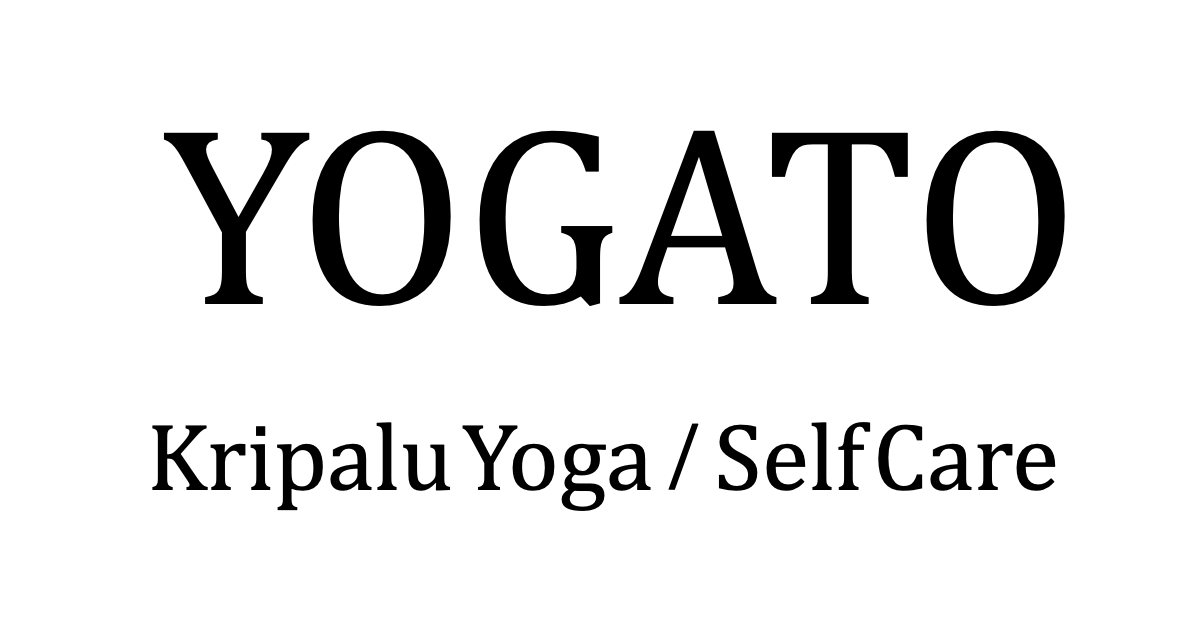<良い意味で、人間(からだ)は鈍感だ>
私たちのからだは、本当によくできています。
不思議なくらい、よくできている。
ひどい腰痛があるときに、肩こりに気がつかない。 その逆もあります。
ふたつの苦痛を同時に感じていたら、
きっと毎日は立ち行かなくなってしまう。
これは、脳や神経の働きによって、
私たちの感覚がある程度“絞り込まれて”いるからです。
「今はこの痛みだけに意識を向けよう」
「この不快感は一時的に横に置いておこう」 そんなふうに、
脳が情報を取捨選択してくれるおかげで、
私たちは日々を乗り越えられているのかもしれません。
これは「ゲートコントロール理論」とも関係があり、
より強い刺激や緊急性の高い情報を優先することで、
私たちの注意を守っている仕組みでもあります。
※詳しくは日本医事新報社さんの記事がわかりやすくまとまっています。
参考にここに上げさせていただきますね。
他にもこのサイトにはわかりやすく「心とからだ」に関する論文を探せるので
私はお世話になっています。おすすめです☺︎
この「感じなくさせる」働きは、からだの“鈍感さ”でありながら、
とても賢く、やさしい機能でもあるのだと思います。
たとえば、日常的にとてもよく使っている手や腕。
スマホを握る手、パソコンを打つ指先、料理、
買い物、抱っこやおんぶに介助・・・
私たちは、一日に何百回、何千回と手や腕を使っています。
本来なら、それだけ動かしているのですから、
疲れや痛みにもっと気づいてもよさそうなもの。
けれど実際には、多くの人が「気づかない」まま日々を過ごしています。
では、なぜなのか?
それは、脳が“慣れ”によって感覚を抑えてくれているから。
これを“感覚順応”や“感覚抑制”と呼びますが、
つまり、使う頻度の高い部位は、
少々疲れていてもすぐには「痛い」と知らせてこないのです。
これは一種の“ありがたい鈍感さ”。
ささいな疲労や違和感をいちいち感じ取っていては、
細かい作業などできなくなってしまいます。
けれど、この鈍感さゆえに、
知らず知らずのうちに手や腕がこわばり、
その影響が肩こりや首の張り、さらには頭痛へとつながっていく。
つまり、首や肩に「感じている」不快感の本当の根っこは、
あまり感じられていない場所・・・
手、腕、前腕の疲労や過緊張にあることも少なくないのです。
ヨガのクラスの中でも、手や腕をゆっくり動かしてみたり、
手の甲や指先に触れてみたりすると、
「えっ、こんなところが痛かったんだ」
「自分の腕ってこんなに固くなっていたんだ」 という驚きや発見があったりします。
それは、自分の“鈍感さ”に対して気づきの扉が開いた瞬間。
日常ではあえて見過ごしていた感覚が、浮かび上がってくるのです。
クリパルヨガでは、こうした「内側の感覚」に
やさしく気づいていくプロセスを大切にしています。
ポーズがきれいにできているかではなく、
今、自分はどんな呼吸をしているのか。 どこに力が入っているのか、
どんな思考が浮かんでいるのか。 “感じていなかったこと”を思い出すように、
自分自身を観ていく。
それは、凝り固まったからだや感覚をほどいていくプロセスであり、
がんばりすぎていた日常の自分に、
そっと手を差し伸べるような時間でもあります。
からだは、感じたときに気づいてあげれば大丈夫。
急ぐ必要も、責める必要もありません。
「良い意味で、人間(からだ)は鈍感だ」
その鈍感さに守られながら、わたしたちは今日も生きている。
そして時々、その鈍感さの奥にある、
本当の声にやさしく耳をすませる時間を持てたなら、
そこからほんとうの癒しや慈しみが始まるのかもしれません。
こういった視点で、ヨガもセルフケアも同じだと感じて
日々過ごしています。
今日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。