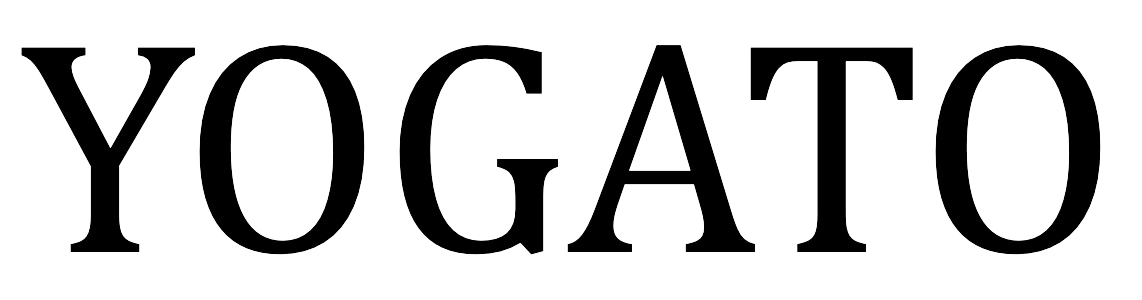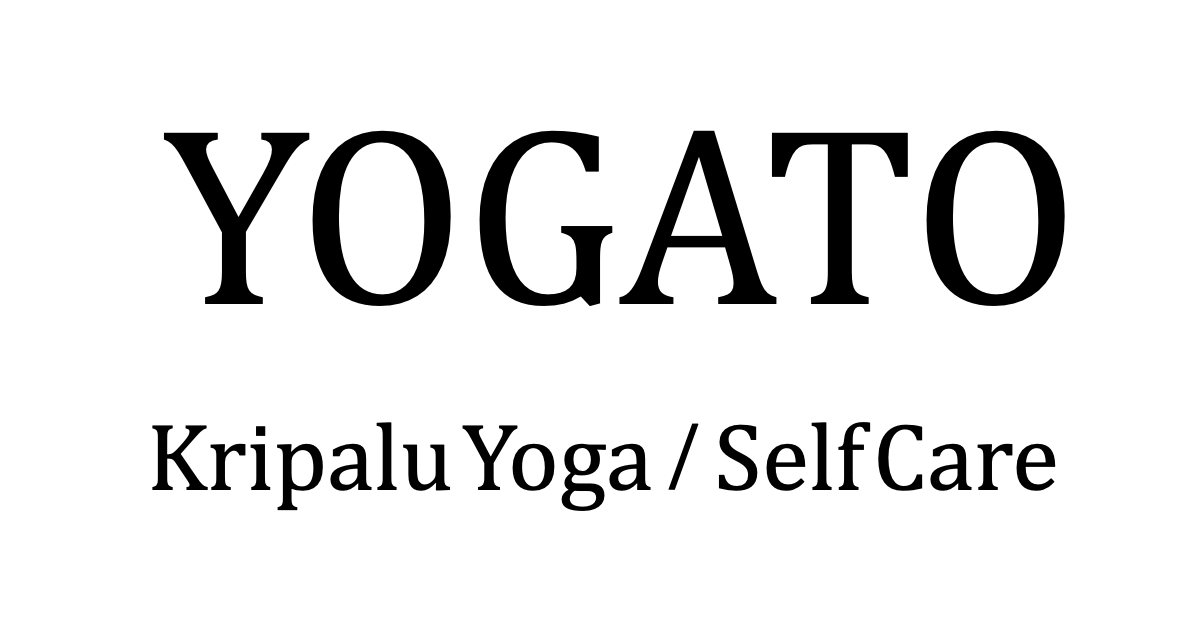<陰陽五行論からみる「春の花粉症」>
春の訪れとともに、多くの人が花粉症に悩まされます。
くしゃみや鼻水、目のかゆみといった症状は、
春の爽やかな季節を存分に楽しめない原因にもなります。
西洋医学では、花粉症はアレルギー反応の一種として捉えられますが、
東洋医学、特に陰陽五行論の視点から見ると、
「春のエネルギーの変化」と「私たちのからだのバランス」の
関係によって引き起こされるものと考えられます。
「アレルギーとして見ない」この視点。面白いなと私は感じます。
・ ・ ・
陰陽五行論では、春は「木」のエネルギーが高まる季節であり、
「木」に属する臓腑は「肝」です。
肝は血を蓄え、
自律神経を調整する働きを持つため、
春になると肝のエネルギーが活発になり、
それがバランスを崩すことで様々な不調が現れます。
また、春は「風邪(ふうじゃ)」が強くなる季節ともされます。
風邪(ふうじゃ)は「揺らぎやすく、外からの影響を受けやすい」性質を持ち、
特に鼻や目といったからだの「開口部」に影響を与えやすいと考えられています。
そのため、花粉症の症状であるくしゃみ、鼻水、目のかゆみは、
風邪(ふうじゃ)の影響を受けている状態とも言えるでしょう。
五行では「木(肝)」は「金(肺)」を剋す関係にあります。
これは、五行の「相剋(そうこく)」という考え方に基づいています。
簡単に言うと、「木」が強くなりすぎると
「金」に対してエネルギーを過剰に与えると考えられています。
具体的には、春に肝のエネルギーが過剰に働くと、
肺の働きが抑えられてしまうことがあります。
肝のエネルギーが強くなると、
肺が本来持っている「防御機能」や「免疫力」が低下しやすくなるため、
アレルギー反応や花粉症などの症状が現れやすくなるのです。
肺は外気を取り込み、からだの防御機能を担う「衛気(えき)」を司る臓腑です。
肺の働きが低下すると、外部からの刺激に弱くなり、
アレルギー反応が起こりやすくなります。
特に、ストレスや睡眠不足、不規則な生活は肝のエネルギーを高め、
結果として肺の機能を弱める要因となります。
この時期は「よく寝ること」「快眠」めちゃくちゃ大事な時期です。
肝気の滞りが続くと、気血の巡りが悪くなり、
花粉症の症状が慢性化しやすくなります。
ではどう対応するのがいいのか?
陰陽五行論の視点から花粉症を軽減するためには、
「肝のバランスを整え、肺の働きを高める」ことが大切です。
以下の養生法を日々の生活に取り入れてみましょう!
● 肝の気をスムーズに流す
・適度な運動や深呼吸、ストレッチを行い、肝の気の流れを整える。
・ヨガや太極拳のような、ゆったりとした動きを取り入れる。
・春菊、菜の花、ほうれん草などの緑の春の食材を積極的に摂る。
● 肺を強化し、衛気を高める
・温かい食事を心がけ、冷たい飲食物を控える。
・生姜やネギ、味噌汁などの温性の食品を取り入れる。
・大根、れんこん、白ごまなどの白い食材を摂り、肺を潤す。
● 「風邪(ふうじゃ)」の影響を受けにくくする
・風の強い日は、首元を温めることで風邪の影響を軽減する。
・加湿を心がけ、鼻や喉の粘膜を守る。
冬から春の養生でお伝えしている内容がそのまま当てはまります。
花粉症は単なるアレルギー反応ではなく、
春のエネルギーの変化とからだのバランスの崩れが関係していると考えられます。
特に「肝の高まり」「風邪の影響」「肺の弱り」が主な要因となるため、
これらを整えることが、症状の軽減につながります。
対策を見てみると、、、
冬から春の養生でお伝えしている内容がそのまま当てはまりますね。
そして
意外に簡単にできることが多い。
花粉症対策、意識的にやってまいりましょう!
私は昨年、全然冬から春の時期
「肝の気をスムーズに流す」の部分ができておらず、
酷い「目と首のかゆみ」に悩まされました。
(昨年は最終的に自分では治せず、皮膚科でお世話になりました。)
今年は「ちょっとかゆいかな?」くらいで抑えられていて、
比較的軽い状態です。
日々バランスよくヨガをして動くことや歩くこと、
セルフケアを続けること。
そして、白湯を意識的に多く摂ることが特に効いていそうです・・・
毎晩のお味噌汁やお吸い物も、欠かさないようにしています。
あーやっぱり日々の暮らし、
養生が大事なんだなーと自分のからだの変化をみても感じています。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。