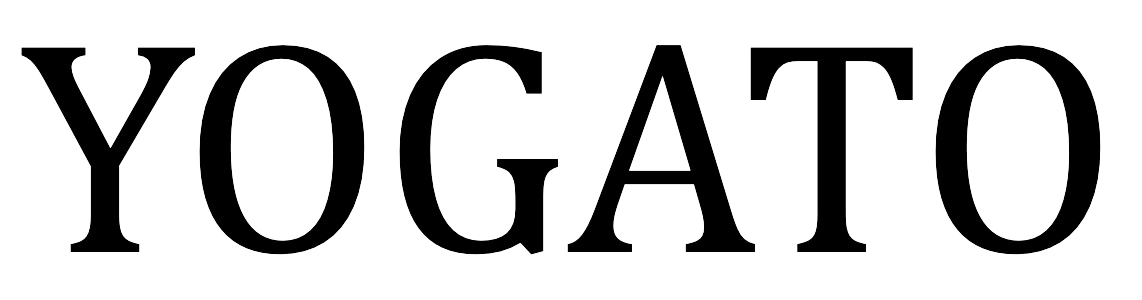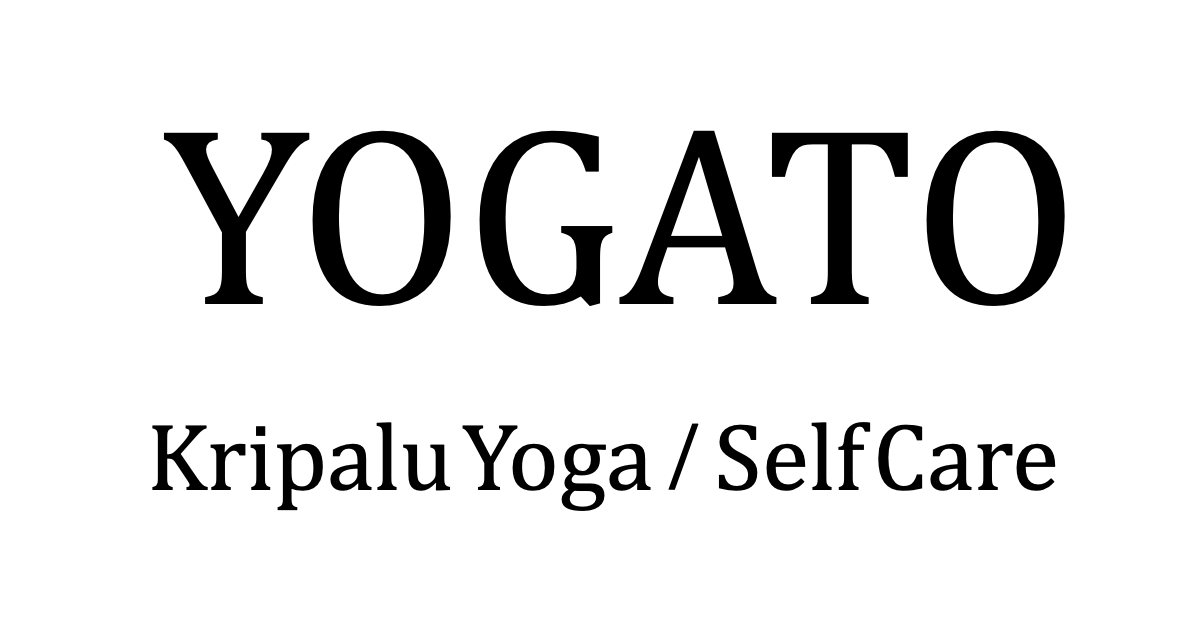<後屈のヒントと大人のヨガ>
後屈のポーズを練習しているとき、
「腰が痛い」「胸が開かない」「首だけ反ってしまう」
そんな感覚を経験したことはありませんか?
それらの違和感や偏りには、骨盤の傾きが大きく関わっています。
特にポイントになるのが、骨盤を『後傾させる』こと、
そして『恥骨でマットを押す』という意識です。
骨盤の角度が変わると、全身が変わる
「プレスポイント」を全方向に確実に向けることができるようになり、
上半身が楽に後に動き始めます。
仰向けやうつ伏せで寝たときに、
骨盤を後ろに倒す(=後傾)という小さな動きは、
背骨全体のカーブに大きな影響を与えます。
(仰向けで骨盤後傾させるという動きは、
腰とマットの隙間を完全に無くす動きです。橋のポーズでこの動きを使います。)
もし骨盤が前に倒れたまま(反り腰の状態)で後屈をすると、
腰にばかり負担がかかり、肋骨は開き過ぎた状態になります。
この状態で後屈に入ると
胸が開きにくくなったり、首だけが反ってしまったりします。
でも、骨盤を少し後ろに傾けて、
恥骨をマットにそっと押し沈めるように意識すると——
腹筋が程よく働き始め
背骨が下から順に整い
胸椎や肩甲骨まわりが自由に動くようになります
すると、「腰が頑張る後屈」から
「全身でひらく後屈」へと変わっていくのです。
前屈の「きそきそよーが」と同様に、もちろん
パッと見た目では変化がわからない場合もありますが、
呼吸のしやすさや安定、全身のバランス、心の落ち着き・・・
といった視点で見た時どちらが深まっていると言えるでしょうか?
「恥骨を押す」と、自然と起こることがあります。
「恥骨を押す」「骨盤が後傾」とは、身体で何が起こっているのか。
骨盤が後傾すると、
下腹がさりげなく引き締まり、内側からの支えが生まれる。
そして背面の臀部やもも裏は働き、
足先までの意識も向くようになります。
下半身が安定し、腰に負担のかからない背骨の状態になるから、
無理なく胸が開き、肩が自由に、呼吸ものびのびと広がっていきます。
まるで、内側からじんわりと広がっていくような後屈です。
ヨガの後屈は、決して「反る」ためのポーズではありません。
むしろ、背骨や前面を「ひらく・伸びる」感覚を大切にしたい。
現代の生活では、前かがみになる姿勢が多く、
胸がすぼまり、呼吸が浅くなりがちです。
だからこそヨガの時間では、背骨がゆったりと広がり、
呼吸が全身に届くような後屈を目指しませんか?
そのための第一歩が、骨盤の角度なのです。
そして、恥骨でマットを押すという、小さな意識です。それだけです。
今回の「きそきそよーが(後屈編)」では、
この骨盤の動きを丁寧に観察しながら、コブラのポーズで変化を見ました。
「恥骨を押す」という意識があるだけで、
ポーズ全体がやさしく、力強く、安心感のある広がりに変わります。
身体の使い方が変わると、心もふわっとひらいていくのです。
・ ・ ・
今日のクラスの後にもお話ししたのですが、
こどもの頃や若い頃、私たちは“とにかく動く”ことで、
知らないうちにからだに「感覚」を刻んでいくことができました。
いわば、「感じる」が先にあり、
そこにからだが自然と順応していくような時期です。
でも歳を重ね大人になると、少し事情が変わってきます。
これまでの人生で積み重ねてきた経験や習慣が、
からだの使い方にも“自分なりのパターン”として染みついています。
たとえば、仕事での姿勢、育児や介護で身についたクセ、
無意識に身構える緊張、過去のケガや不調からくる動きの制限…。
そうした「経験の蓄積」は、時に、新しい動きを受け入れるときの
“フィルター”や“壁”となり、素直な感覚の流れを妨げてしまうことがあります。
だからこそ、大人には「感じる」だけでなく、
“なぜその動きが必要なのか?”
“どうしてこの姿勢になるのか?”
という理解をともなった体験がとても大切になってくると思うんです。
理論的に知り、視覚的にイメージし、実際に動いてみる。
頭と心とからだが一致したとき、はじめて私たちは深く納得し、
心地よさも伴いながら変わっていけるのです。
そして、その“理解を伴った体験”は、
これまでのフィルターや壁をやさしく越えて、
私たち自身を次のステージへと「変化・変容」させる、大きな力になります。
知識と感覚、体験。これらが全てつながった時の
大人の持つエネルギーはすごいのです!
「きそきそよーが」
かわいらしいクラス名ですが、実はとても大人なヨガです。
小さなからだの感覚を大切にしながら、
やさしく、確かな変化を積み重ねていく・・・
そんな時間をご一緒できることに、心から感謝しています。
その感覚を楽しみながら続けて参りましょう!
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。