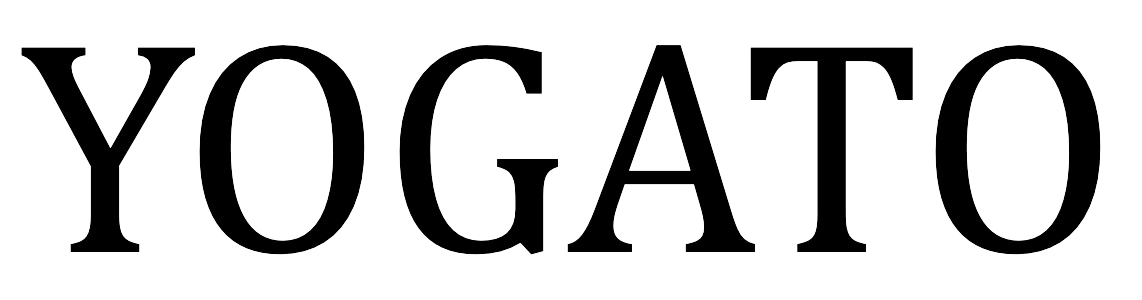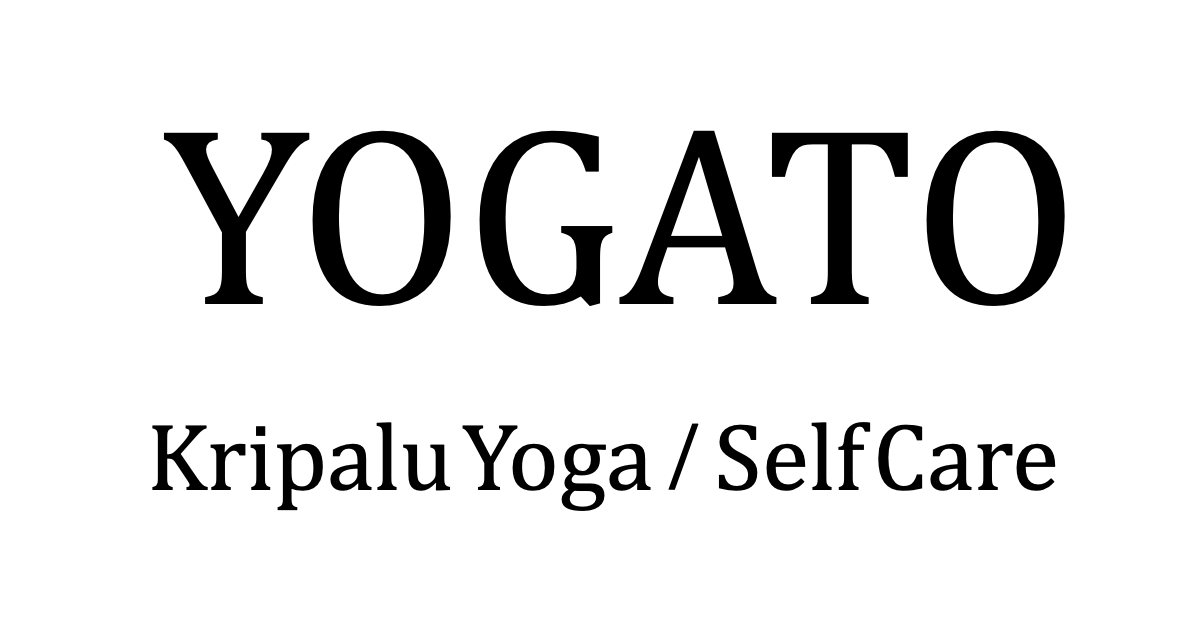<夏土用、脾経とわたし>
夏土用とは、立秋の直前、およそ18日間の時期。
一年の中でも特に暑さが厳しく、湿度も高くなり、
自然界には“熱と湿”が満ちてきます。
その影響は、わたしたちのからだにも静かに現れます。
からだがだるい、足がむくむ、頭がぼんやりする、やる気が出ない……
そんな声が多く聞こえるのも、この時期ならではかもしれません。
東洋医学では、この季節の変わり目に
最も影響を受けやすいのが「脾(ひ)」だとされています。
“脾”という名前にあまり馴染みのない方も多いと思いますが、
実を言うと、私自身も最初に「脾経」という言葉を学んだとき、
まずは「それってどこ?」
そして「どう関係するの?」と半信半疑でした。
けれど、季節のうつろいや日々のからだの調子に意識を向けるようになって、
この“脾”がいかに繊細に、そして深くわたしたちを支えているかを、
少しずつ実感するようになりました。
東洋医学における脾は、現代医学の“脾臓”とは異なります。
(この部分の理解が大事でした。別途7月中に書きますね)
「脾経」の“脾”は主に「消化吸収」「水分代謝」「気血の生成」、
そして「思考のまとまり」などをつかさどります。
臓器というよりもこういった働きを担う私たち身体のシステムなのです。
五行でいうと「土」に属し、大地のようなどっしりとした安定感をもつ存在です。
その一方で、湿に弱く、ためこみやすいという性質も。
梅雨の時期と同じ考えがここにあります。
だからこの時期、冷たいものや甘いもののとりすぎ、考えごとや心配ごとは、
脾にとって負担になりやすいのです。
なんとなくやる気が出ない、からだが重たい、胃がもたれる、
頭の中がとっちらかってまとまらない……
そんなとき、もしかすると、脾がそっと助けを求めているのかもしれません。
脾経の場所は足先から始まります。
足の親指の先(内側)からはじまり、
足の内側の縁に沿って、内くるぶしの前を通り、
すねの内側、膝の内側、太ももの内側をのぼっていきます。
そのまま下腹部に入り、おへその横あたり体幹部分を通って胃のあたりを支え、
胸(脇の下あたり)までつながっています。
このラインに触れていくことは、ただからだを整えるだけでなく、
心とからだの“真ん中”をやさしく整えていくような感覚があります。
私自身、頭の中がぐるぐるしていたり、
なんだか浮遊感があって“ここにいない”感じがするときほど、
脾経の流れをなでたり、土踏まずをやさしく押してみたりします。
すると、不思議と呼吸が落ち着き、思考も自然とまとまりはじめるのです。
また、脾の不調は“外に出せない”という感覚にもつながりやすいと言われます。
からだにこもった湿や熱。
思考にたまった不安や焦り。
そうした“内にためこんでしまうもの”を、どう外へ流していけるか。
それこそが、この夏土用という時期のセルフケアの大きなテーマになります。
先日のクラスでもご紹介した“自前のクーラー”。
ウエスト・肋骨・胸をひらくことで、こもった熱や湿をからだから外へ出していく。
このケアと、脾経を整えるというテーマはつながっています。
https://yogato.jp/<夏のからだに風をとおす-暑さ対策「ウエスト/
この夏土用。
ぜひ、からだの内側にそっと意識を向けてみてください。
湿と熱がどこにあるか。どこが重たいか。どこが落ち着かないか。
まずはじぶんを観察してみる。
そこにやさしく手を添えるように、脾経をさわさわとなでてみる。
胸や肋骨が開くように、意識的に呼吸を動かしてみる・・・
それは、自分自身の“真ん中”を見つめ直す、
静かな対話の時間になるかもしれません。
今日も最後まで読んでくださり、ありがとうございます。