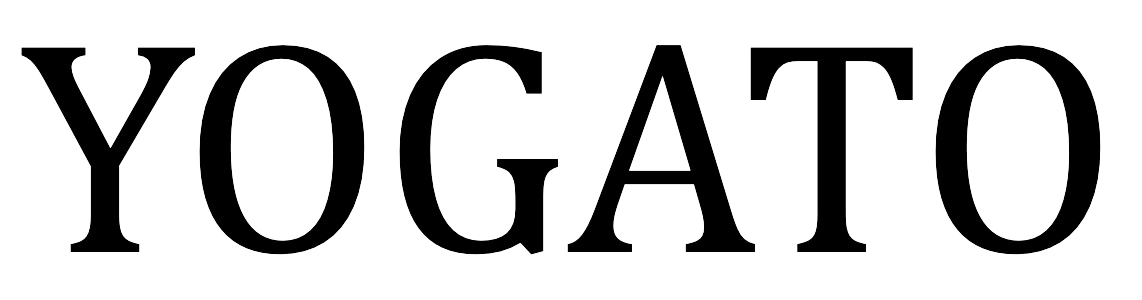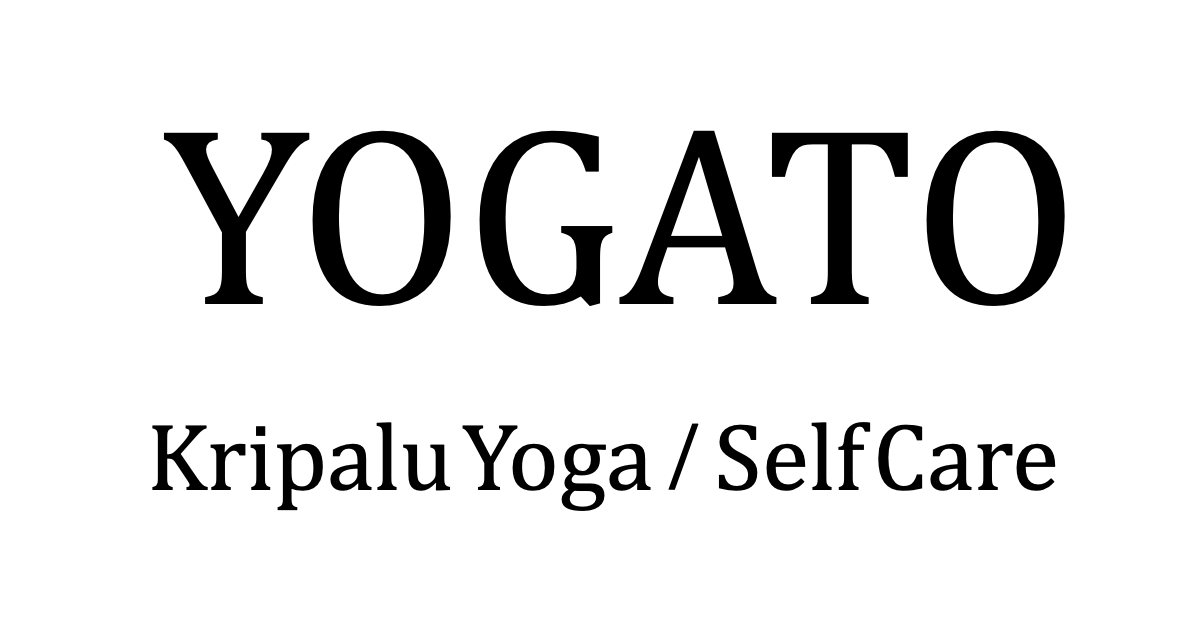<全身でひらく、全身で折りたたむ——開脚前屈の本質へ>
ウパヴィスタ コン アーサナ(座位の開脚前屈)は、
一見すると脚を左右にひらいて、上半身を前に倒すだけのように見えるかもしれません。
でも今日の朝のクラスでは、このポーズを「リラックス」ではなく、
「全身を使って行う前屈」としてとらえ、プレスポイントの意識を深めていきました。
この考え方は、基本の座位前屈(パスチモッターナーサナ)と変わりません。
脚を前にそろえた前屈でも、脚を左右にひらいた前屈でも、
大切なのは「坐骨で床を押す」「脚を働かせる」「背骨の流れを感じる」といった、
からだの中心から全体をつなげていく感覚です。
とくにポイントになるのが、脚の使い方。
開脚していると、脚は“ただ広げているだけ”になりやすく、
力が抜けたまま前に倒れようとしてしまうことも。
でも、だからこそ意識したいのが、
「足裏・踵を外へ押し出す(つま先上向き)」
「坐骨は床を押し下げて、腰をのびやかに保つ(前後上下・全身使っている状態)」
「脚の裏も床方向に押す(できる場合)」
というような、丁寧なプレスの感覚です。
動きの中では、「倒れる」より「大地へ根をはる」ような感覚。
骨盤の底から脚を通して、地面へと広がっていく力を感じながら、
自然と上半身が導かれていく——そんな前屈です。
ここで、よくある違いについても少しふれておきたいと思います。
いつもクラスでお伝えしているのですが、「リラックスした前屈」と
クリパルヨガの「全身を働かせながら入る前屈」は、見た目が似ていても、
からだの内側で起きていることはまったく違います。
開脚の前屈も同じです。
以前、「ベターッと開脚」という言葉が流行したことがありました。
ヨガをしていると、この開脚を目にすることがあります。
つま先を内に倒して、胸やお腹を床へ近づけようとするアプローチは、
どちらかというとからだを“預ける”ような前屈。
一方で、プレスポイントを使って全身で前に向かうときは、たとえ深く倒れていなくても、
内側にはしっかりとした土台と広がりがあります。
どちらが正しい、ということではありません。
でも、「今、わたしはどんなふうにこのポーズに向かっているだろう?」と、
やさしく問いかけながら練習することで、からだの奥にある感覚が目を覚ましはじめます。
・ ・ ・
以前、わたし自身もこのアーサナを改めてじっくり味わってみて、
はっとした気づきがありました。
「わたし、想像以上に下半身が弱いんだ!!!」と。
開脚して前屈しようとすると、意識はつい上半身にばかり向いてしまって、
脚が“そこにあるだけ”になっていたことに気がついたのです。
この体験は、わたしが学んでいる整体の「手当て」とも自然に重なっていきました。
私が学んでいる「手当ての施術」では、施術をはじめる前に、
まず自分自身の上下のバランスを整えます。これ、誰でもできます。
合掌して座り、足裏も合掌。と頭頂を感じながら、
上半身と下半身の両方がちゃんと使えているか、呼吸を通して整えていくのです。
これはまさに、クリパルヨガでポーズの取り方とよく似ています。
力んでいるわけではない、でも注意深く、上下どちらも使っている・・・
自分の今を観察していくようなあのひととき。
「上下どちらも使って、今ここにいる」という感覚が、動きの土台をつくってくれます。
この準備が整うと、不思議と手のひらがほんのりあたたかくなってくるんです。
でも、わたしは最初、この手当てがとても苦手でした。
十分足元も使っているつもりだけど、「足元」がふらふらしていたからだったんですね。
下半身がしっかりと使えていないまま、
上半身だけで何かをしようとしていたことに、あとから気づいたのです。
ウパヴィスタ コン アーサナで感じた“脚を通した安定感のなさ”は、
そのまま整体の場面にも表れていたんだな、と、あらためて実感しました。
プレスポイントを意識してポーズをとること。
それは、からだの形を整えるためだけでなく、
内側の感覚を育てていくための、大切な手がかりになるのです。
脚のうしろ、坐骨、背骨、手のひら。
どれかひとつではなく、全体が少しずつつながっていくように——。
ポーズの中でふと感じたことが、そのまま日常のなかでの
“わたしのあり方”を見せてくれるような、そんな体験でもありました。
ヨガの中で、手当ての中で、
プレスポイントをたよりに、もう一度自分のからだに戻っていく。
この循環があるかぎり、感覚はきっと、ゆっくりでも育っていく。
そんなことを、静かに感じた朝の時間でした。
まだ私はこの座位の開脚前屈は苦手です。
これから一歩一歩また探求して参ります。
どうぞご一緒に!
今日も最後まで読んでくださり、ありがとうございます。