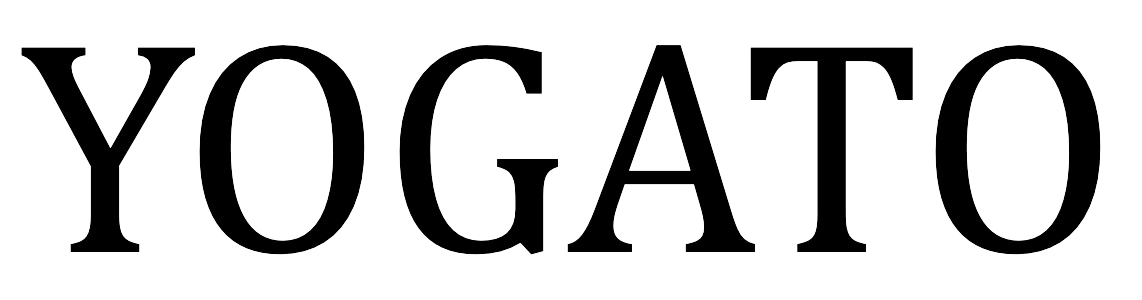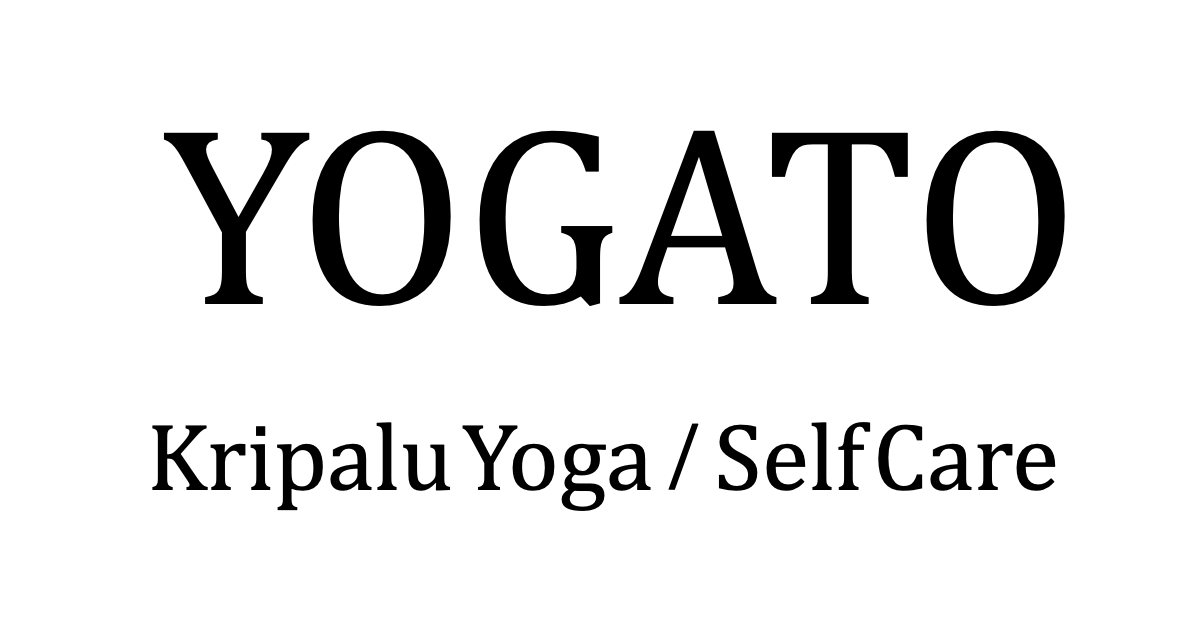20250130
<二十四節気とはー陰陽五行論との関係>
私たちの暮らしに寄り添う季節の暦——それが二十四節気です。
太陽の動きをもとに1年を24の節目に分けたこの暦は、
春分や秋分といったおなじみの節気を含み、
立春から始まります。
日本では古くから農業や生活の指標とされてきましたが、
現代においても、自然のリズムを感じながら暮らすための
大切な道しるべとなります。
他の季節の暦との違い
日本には、旧暦(太陰太陽暦)、七十二候、雑節など、
季節を表すさまざまな暦があります。
旧暦は月の満ち欠けを基準にして、
現在の新月を1日とする暦とは異なります。
七十二候は二十四節気をさらに細かく三つに分け、
五日ごとの微細な季節の移ろいを表します。
雑節(彼岸や土用など)は主に農作業や行事の目安として用いられます。
この中でも二十四節気は、『太陽の軌道』を基にした暦であるため、
現代の暦ともズレが少なく、季節感を感じやすいです。
東洋の伝統的な自然観である陰陽五行論とも、
二十四節気は深く結びついています。
陰陽は、自然界のすべてのものが「陽」と「陰」という
相対するエネルギーのバランスで成り立つという考え方です。
春から夏へ向かう陽の季節、秋から冬へ向かう陰の季節
この流れの中で二十四節気は刻まれています。
東洋の伝統的な自然観である陰陽五行論とも、
二十四節気は深く結びついています。
陰陽は、自然界のすべてのものが「陽」と「陰」という
相対するエネルギーのバランスで成り立つという考え方です。
春から夏へ向かう陽の季節、
秋から冬へ向かう陰の季節
この流れの中で二十四節気は刻まれています。
さらに、五行(木・火・土・金・水)の視点で見ると、、、
春は「木」、のびのびと上へと伸びる成長の陽のエネルギー。
夏は「火」、ぱーっと広がる強い陽のエネルギー。
秋は「金」、きゅっと、表面は硬く中は柔らかいような陰のエネルギー。
冬は「水」、ぎゅーっと、芯が硬く、外は柔らかいような内側へと集まる強い陰のエネルギー。
そして、それらをつなぐ土用の時期は「土」とされ、「調和」の性質を持っています。
(土の擬音も知りたくなりませんか。それはまた次の機会に✨)
それぞれの季節には、五行に対応する色・食べ物・養生法があり、
それを意識することで心身のバランスを整えることができます。
・ ・ ・
7年ほど前、私はこの陰陽五行論を学び始めました。
きっかけは、身体の不調を抱え、「痛いだらけだった」自分を
何とか変えられないかと、試行錯誤していたことでした。
実際に生活の中で取り入れてみると、
「今の私はどこに偏っているのか?」
「どの要素を足せばいいのか?引けばいいのか?」と、
自分の暮らしを見つめるようになりました。
そんなふうに過ごしているうちに、自然と「二十四節気」に近づいていったのです。
現代はカレンダーがあれば季節を知ることができますが、
本当の意味で「季節を感じる」とはどういうことでしょうか。
日差しの強さや暖かさ、微細な変化、
空気の冷たさ、風のにおい、鳥のさえずり、、、
それらを肌で感じることこそ、
二十四節気の本来の意味に近いかもしれません。
例えば、今まさに「大寒」の時期は、
一年でもっとも寒さが厳しい頃。
でも、空気が澄んで、凛とした朝の気配の中に
春の兆しを小さく感じることもあります。
少しずつ夕方、夕日の時間が長くなってきていることにも気が付きます。
「立春」になれば、まだまだ冷たい風の中にも、
ふと柔らかさを感じる瞬間があるでしょう。
そんな小さな変化に気づくことで、
私たちの暮らしはもっともっと豊かになります。
季節の変化に耳を澄ませることは、
自分の内側の変化にも気づくことにつながります。
冬の寒さに肩をすくめる日々が続いていたら、少しだけ肩の力を抜く。
春の芽吹きを見つけたら、自分の中の新しいエネルギーにも目を向けてみる。
自然のリズムを意識することは、忙しい毎日の中で、
自分でじぶんを整え、養うことにもつながるのです。
あー、、それがYOGATOのやりたいことなんだなーそう思って
「ヨガと暦と。」をブログに書きはじめました。
今年の二十四節気、皆さんはどんなふうに感じますか?
暮らしが豊かになるエッセンスになりますように。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。