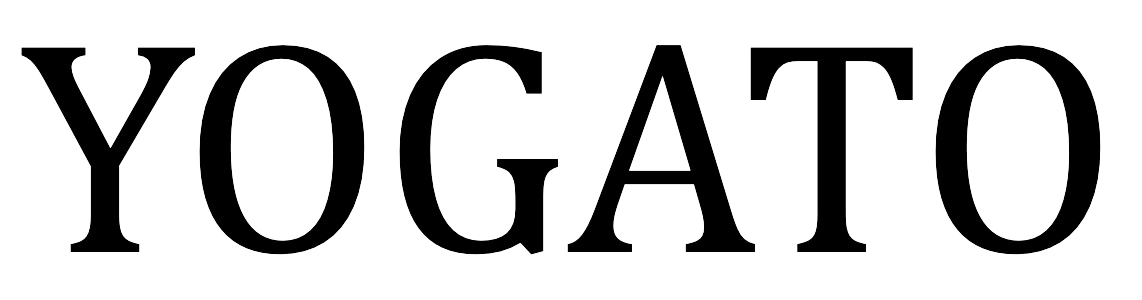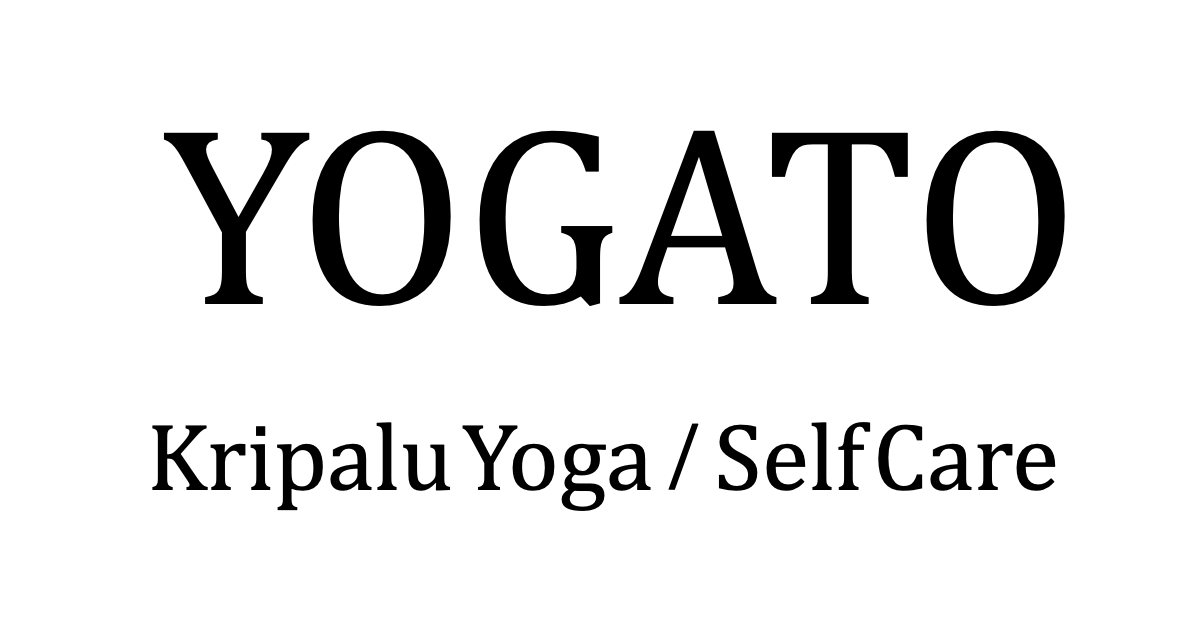<「過剰」の裏にある「不足」を探る〜甘いものを欲するとき 〜>
甘いものが無性に食べたくなるとき、皆さんはどんな状態でしょうか?
疲れているとき、ストレスが溜まっているとき、
あるいはなんとなく気分を上げたいとき?
この「甘いものを欲する」という現象を、
陰陽五行論の視点から考えてみると、
「土」のエネルギーが過剰になっている可能性があります。
陰陽五行論において、「土」は安定や養う力を象徴します。
そして「甘味」は、五行の「土」に属する味。
つまり、甘いものを欲するのは、
「土」のエネルギーが必要だから、ともいえます。
しかし、ここで大切なのは、「過剰」の裏には「不足」があるという視点です。
・ ・ ・
何かを強くを欲するときには何が「不足」しているのでしょうか?
陰陽五行論において、何かを「強くを欲する」過剰のときには
何かが「足りていない」不足の状態が隠れています。
今回は「甘味」。五行の「土」でみてみましょう。
・エネルギー不足(気虚)
疲れがたまり、身体がエネルギーを欲している。
特に脾(消化吸収を司る)が弱っていると、甘いもので補おうとすることがあります。
・安心感の不足
「土」は安定のエネルギー。
心が落ち着かず、不安定なとき、
甘いものを食べることでほっとした気持ちになろうとすることがあります。
「甘」の性質をとることで中庸、バランスを自然に取ろうとするのです。
・人とのつながり(愛情)の不足
甘いものを食べると、幸せホルモンといわれるセロトニンが分泌されます。
これは人との温かいつながりを感じたときにも増えるもの。
もし孤独感や寂しさがあるなら、
甘いものでその不足を埋めようとしているかもしれません。
・思考の過剰
陰陽五行において、土のエネルギーが過剰になると、
「思考」が堂々巡りしやすくなります。
それを鎮めようとして甘いものを求めることも起きやすいと言われます。
例えば、勉強や仕事で頭を使いすぎると、
無性に甘いものが食べたくなることがあります。
このように、「甘いものを欲する」背景には、何かしらの不足があることがわかります。
では、ただ甘いものを我慢すればいいのでしょうか?
陰陽五行の考え方では、「過剰」を抑えるのではなく、
「不足」を補うことでバランスを取るのが自然な方法です。
ただ甘いものを制限するのではなく、
「不足」を満たすことが必要なのだと見えてくる。
例えば、
・エネルギー不足なら、十分な休息と滋養のある食事を
ただ甘いもので補うのではなく、バランスの取れた食事を心がけましょう。
特に、脾を養う食材(かぼちゃ、さつまいも、大豆など)を取り入れるのがおすすめです。
・安心感が不足しているなら、自分をいたわる時間を
ゆっくりとお茶を飲んだり、深呼吸をしてみたり。
ただ「食べること」だけでなく、「自分を満たす」方法を増やしてみましょう。
また、ヨガのポーズの「安定」「グラウディング」を見直すときなのかもしれません、
足裏のマッサージや使い方、筋肉の動き、、、そんな視点でみてみるのもおすすめです。
・人とのつながりが不足しているなら、誰かと温かい時間を
一緒に食事を楽しむ時間を作るだけでも、心が満たされます。
思い切って、休む。誰かと会って話すことを楽しむ。大事ですね。
第4チャクラへのセルフケアや、胸を開くポーズもおすすめです。
自分に愛を向ける、大切にする。
・思考の過剰を鎮めるには、からだを動かすことも大切
ヨガや軽いストレッチ、散歩などを取り入れることで、
思考のバランスを取ることができます。
・ ・ ・
「甘いものをどうしても食べすぎてしまう」
「最近、間食が増えたかな?」 そう感じたときこそ、
自分の心と体の声を聞くチャンスです。
「本当に足りていないものは何か?」
この問いを持つことで、ただ食べることに頼るのではなく、
根本的なバランスを整えていくことができます。
甘いものが欲しくなったとき、
それは何かが足りていないサインかもしれません。
今回は「土の過剰」の代表例である「甘味」で書きました。
他の「木火金水」これらの性質で見ると大まかですが
これらのように特長をあげることが出来ます。
「活動的すぎてうるさい!」(木の過剰)
不足しているもの:「休息」「落ち着き」「柔軟性」
「性欲がつよすぎる!」(火の過剰)
不足しているもの:「心の満足感」「愛情」「自分自身への受容」
「完璧主義すぎて人に任せられない!」(金の過剰)
不足しているもの:「柔軟性」「人への信頼」「流れに任せる力」
「未来が不安で貯金ばかりしてしまう!」(水の過剰)
不足しているもの:「安心感」「信頼」「今を楽しむ力」
こうして見てみると、なんとなく使えそうな感じがしませんか?
性格の特徴を陰陽五行論に照らしてみるのです。
自分の場合は気になる「過剰」と「不足」はありましたか?
陰陽五行論にはさまざまな視点があります。
そして、すべての人に当てはまる正解があるわけではありません。
ですが、「過剰」の裏にある「不足」に気づくこと。
ただ、「過剰」の裏にある「不足」を見つめることで、
より自然で、自分に合った方法で整えていくことができるのです。
「過剰」に気づいたら、「不足」とも寄り添い、
心とからだのバランスを整えていけますように。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。