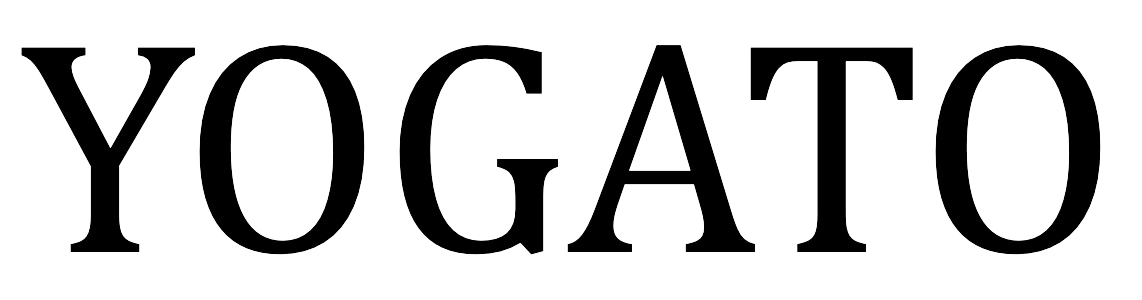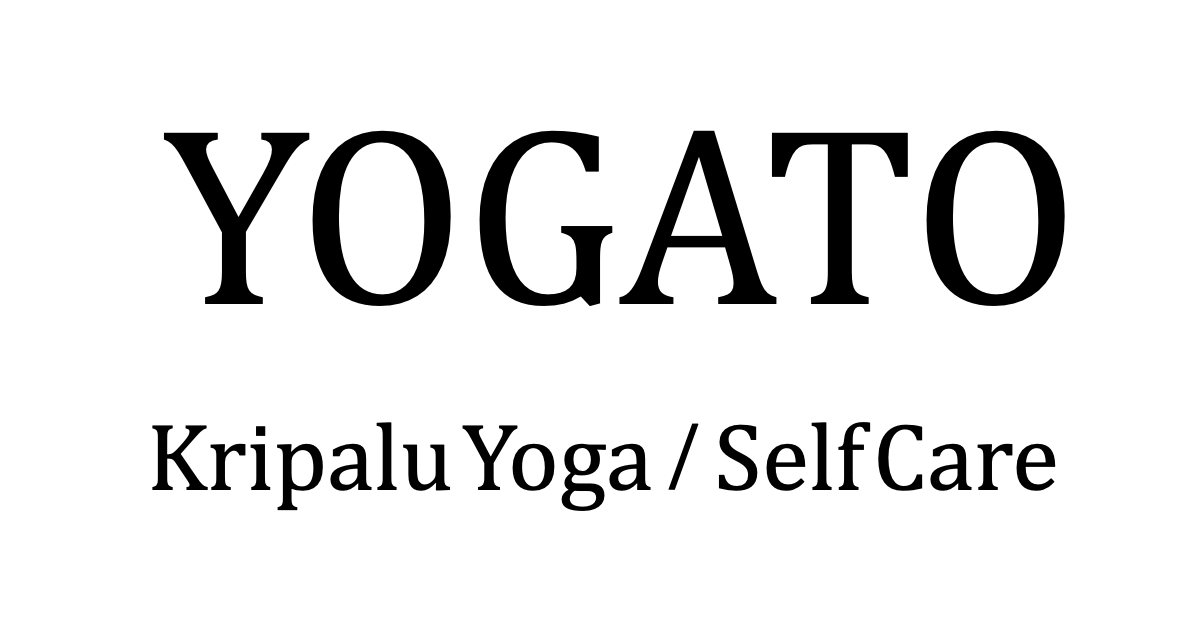<「のどの不調・風邪対策」には中府を緩める>
寒さ厳しい、のどの不調や風邪の症状が気になる最後の季節。
そんなときに意識したいのが、肺経のツボ「中府(ちゅうふ)」です。
中府を緩めることで、呼吸が深まり、咳やのどの違和感が和らぐことがあります。
「中府」は、鎖骨のすぐ下、肩の内側あたりに位置するツボで、
もう一つすぐそばにある「雲門」と一緒に覚えると便利で場所も見つけやすいです。
●雲門と中府の位置
雲門と中府は、どちらも肺経のツボで、すぐ近くに並んでいます。
雲門は鎖骨のすぐ下、肩の前側のくぼみにあるツボです。
中府は雲門のすぐ下にあり、(親指の幅一個分ほど下)胸のつけ根に近い位置にあります。
雲門は特に胸を開き、肺の働きを活性化するツボであり、
中府とセットでほぐすことで、呼吸が深まりやすくなります。
また、肩や腕の付け根の緊張を解放し、肺経の流れを促す役割もあります。
補足として、、、
・雲門を緩めると、鎖骨周りの詰まりが取れやすい
・中府を緩めると、胸の奥まで呼吸が入りやすくなる
中府が『肺経』のスタート地点にあたります。
・ ・ ・
肺経(はいけい)は、東洋医学において「肺」の働きを調整する経絡の一つです。
胸から腕の内側を通り、親指へとつながっています。
肺経が滞ると、呼吸の浅さや咳、風邪をひきやすくなるだけでなく、
肩のこりや腕のだるさ、手の冷えなどにも影響を及ぼします。
特に、中府周辺の緊張が強いと、胸郭の動きが制限され、
肩や腕にかけて張りや痛みを感じることが増えるのです。
これは、肺経の経路が胸から腕へと流れているためで、
中府の緊張が緩むことで、腕全体の巡りも改善されます。
また、中医学では『肺は皮毛を主る』※と言われ、
肺の状態が肌や粘膜のバリア機能にも影響を与えると考えられています。
乾燥する冬は、肺経を整えることで風邪予防にもつながるとされています。
(※皮膚や体表の毛(体の一番外側のバリア)のことを皮毛と呼びます。)
肺経は、秋と特に関わりが深い経絡ですが、
季節を問わず一年を通して意識したい部分です。
特に季節の変わり目は、肺経が影響を受けやすく、
のどの不調や免疫力の低下が起こりやすい時期でもあります。
また、パソコン作業が多い方(胸に緊張が出やすい)や、
上半身の筋力が弱いと感じる方も、日常的に肺経を整えることを意識すると、
肩や腕の疲れが軽減され、呼吸が深まりやすくなります。
●中府を緩めるヨガの動き
ヨガの中には、「中府」を自然にほぐし、
胸を開くのに適した動きがいくつかあります。
今回は、今日のクラスでも行った
「鷲の手の上下の動き」と「ヨガムドラの胸・中府のストレッチ」をご紹介します。
1. 鷲の手の上下の動き
両腕を絡めて鷲のポーズ(ガルダアーサナ)の腕の形を作り、
肘をゆっくり上下に動かします。
肩甲骨の間が広がり、肩や胸の前側がじんわりとほぐれます。
中府周辺の緊張を和らげながら、肩の内側の滞りも流してくれるので、
呼吸が深まりやすくなります。
また、腕の内側のストレッチにもなり、肺経の流れが促されることで、
手の冷えやこわばりの改善にも役立ちます。
2. ヨガムドラの胸・中府のストレッチ
正座や立位で、両手を背中の後ろで組み、
吸う息で胸を開きながら肩甲骨を寄せ、吐く息で上体を前に倒していきます。
この動きは、胸の前側を開きながら、
中府のあたりに心地よい刺激を与えてくれます。
デスクワークや猫背が続いて胸が縮こまっているときにも、
とても気持ちのよいストレッチになります。
また、中府が緩むことで、肺経を通じて腕全体の血流が促され、
肩から手にかけての緊張も和らぎます。
正座ができない時は、立位の前屈で、
前屈できない時は腕だけするのもおすすめです。
腕だけの場合は無理のない範囲で両手を背中の後ろで組み、上下に腕を動かして
中府や胸のあたりに優しい振動を加えてみてください。
・ ・ ・
中府を緩めることで、のどや呼吸の不調が和らぎ、
風邪予防にもつながります。
ツボ押しやセルフマッサージだけでなく、ヨガの動き両方を取り入れることで、
より自然に、心地よく身体を整えることができます。
この季節、寒さや乾燥に負けず、深く心地よい呼吸を保てるよう、
日々のケアに取り入れてみてください。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。